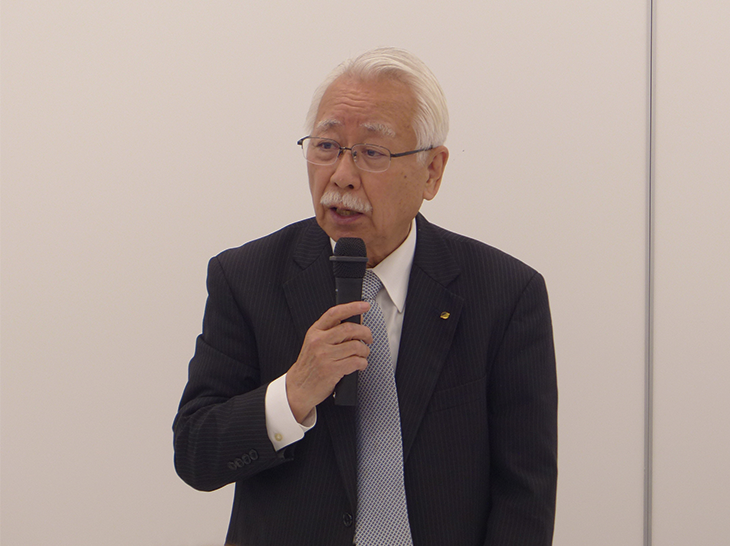HOT NEWS
BA東京が「第10回BA東京美容サミット」を開催
東京都美容生活衛生同業組合(BA東京/金内光信理事長)は、2025年3月26日(水)美容会館(東京都・渋谷区)において、「第10回BA東京美容サミット」を開催した。同サミットは、美容業界の抱える諸課題を業界の共通認識として捉え、毎回さまざまなテーマをもとに業界内外の有識者、関係者を招き美容の未来を語る企画。今回は「変革する美容業界の課題と未来」と題し、2つのテーマ「フリーランス美容師の働き方と社会的補償の充実」「美容師生涯教育のあり方、制度見直しの可能性」を議論した。参加したのは、BA東京の理事をはじめ、フリーランス美容師、フリーランス美容師を雇用するサロン経営者など計12名が登壇し、現状と課題を語り合った。
開催にあたり金内光信理事長は「おかげ様で大きな関心をいただき、今回100名ほどの参加者がお見えで、韓国からも来ていただいている。業界の関心事がテーマになっていますので、大いに議論をしていきたいと思う」と挨拶し美容サミットが開始された。
【パネリスト】
- 寺村優太(株式会社スリー 代表)
- 森越道大(一般社団法人デジタルサロン協会 事務局長)
- 青木大地(COA銀座 代表)
- 間嶋崇裕(AMA TOKYO 代表)
- 力丸朋子(フリーランス美容師)
- 西田智美(フリーランス美容師)
【特別参加】
- 佐藤勢津之(公益財団法人理容師美容師試験研修センター 部長)
※2025年3月で定年退職
【BA東京】
- 金内光信 理事長
- 福島吉範 副理事長
- 石井庸子 副理事長
- 村橋哲矢 専務理事(ファシリテーター)
- 大田文雄 常務理事(司会)
テーマ【フリーランス美容師の働き方と社会的補償の充実】
2020年の調査でフリーランス美容師の数は83,000人で、現在は10万人を超えると予測され、4~5人に1人がフリーランス美容師といわれている。フリーランスの課題とその解決について議論した。
●力丸朋子(フリーランス美容師)
フリーランスになったのは8年前。勤めていた美容室が大好きだったが、お給料が固定給に等しく、社会保障がなかった。また、出産する先輩はキャリアを諦めているのが現状だった。美容師の仕事が大好きだったので将来を思い退職しフリーランスに。フリーランスを経験して思うのは、今は働く環境が整ったサロンが増えたこと。“自分の時間が欲しい”とか、“手取りを増やしたい”という理由だけでフリーランスになるのは、リスクが大きいと思う。今は、女性美容師のコミュニティをつくり、同じ悩みを共有するとともに、企業との連携もスタートし美容師の可能性を感じている。
●西田智美(フリーランス美容師)
フリーランスになったきっかけは、働き方が窮屈になったから。薬剤の縛りや、ミーティングの多さ、休日の社用などさまざまで、中でもお客様からのウェディングのヘアメイク依頼を断らざるを得なかったのは悔しく、変化を求めてフリーランスになった。なってみると、クレジットカードがつくれず、事務仕事の多さに驚きつつ、やはり保障がないことが不安になり、サロン面接を受けたことがあったが、フリーランス経験者はスタッフに影響があると懸念された。今は、力丸さんの女性美容師コミュニティに参加し、商品開発やPRなどを行うほか、男性が多い美容室での女性スタッフのケアをするなど仕事の幅が広がり充実している。
●森越道大(株式会社SENJYU 代表/一般社団法人デジタルサロン協会 事務局長)
SENJYU(美容室20拠点)を運営していて思うのは、今の時代、フリーランスでも社員でも、会社がなくなる可能性はあるので同じ。フリーランスだからとか組織だからとは一概にいえないと思っていて、というのも、SENJYUは社員の他にフリーランスが60人ほど在籍し、全国のシェアサロンや業務委託サロンの席を借りて運営している。SENJYUが力を入れているのは、オペレーション・教育・集客で、徹底したルールと仕組みづくりを行い、普通の会社より組織であると自負している。エリアごとにチーム制で運営し、チームの売り上げを分配する仕組みとなっている。
●青木大地(COA銀座 代表)
COAは全員正社員雇用。自分自身、正社員で長く働いていたが、2年間フリーランスを経験し、COAの幹部も開業前に全員フリーランスを経験してもらった。雇用パターンを全て知りメリットも理解できたが、日本の美容をもっと成長させて発展させたい、美容業界をより良くしたいという思いが強く、そのためには組織化が必須だった。組織を強化するとともに、勤務時間のフレックス制、バックオフィス勤務、自社商品開発、在宅勤務などの雇用を実現している。また、スタイリストとアシスタントを1:3で雇用し、チーム制を取り入れていることで、スタイリストの平均年収1,400万円を達成。「働きやすさ」「収入面」「会社からのサポート」を実施し、2024年12月の銀座店の売り上げは9,500万円を達成した。
●間嶋崇裕(AMA TOKYO 代表)
AMA TOKYOは2年で2店舗展開、6月に新店舗をオープンする予定。業務委託と社員雇用のハイブリッド型のサロンで、うまく運営できている。混在型の良さは、働こうと思えばとことん働け、逆に休もうと思えば月の半分は自由な時間になる点。社員、業務委託、面貸し、この三軸を会社がしっかりつくっていて、例えば、面貸しがいい場合は、うちのブランドも使えるようになっているので、働き方も体験できてフレキシブル。選択肢として選べる環境が社内で確立しているので、逃げ道じゃなくて攻め道になっていると思う。
●石井庸子 副理事長
男女差別ではなく、女性美容師にとっては仲間が必要。というのも、女性の場合、一番の課題は、結婚・出産・子育てにある。なので、私のサロンでは女性スタイリストをサポートしてきた。子供の体調が悪くなったら私がお迎えに行き、病院にも連れていく。何人かのスタッフで交代しながら子供を見ているので、子供にとっても社会性が養われると実感している。今は社会保険がしっかりしているので、育休も長くなる傾向にあり、お客様のことを思うとその子の実力が必要と感じている。そのうえで、子育てをしながら働くには、仲間がいないと難しいと考える。
●寺村優太(株式会社スリー 代表)
約14年前、当時 SNSが出始めたころで、自由にSNSを使えず、くわえて薬剤に制限もあり、お客様のためになることができない環境で、フリーランスの道を選んだ。今日参加しているサロンは、時代に合った働き方を提供されていて、今はこういった魅力的できちんと稼げせるサロンが揃ってきたと思う。また、“フリーランスの保障”という点では、経営者目線だとフリーランスに保障をつけたら辞めてしまうという懸念もあると思うが、正直やりたいことが強い人は辞めるので、本当に能力が高い人が所属しながら働くには、“この人たちと働きたい”“この組織で頑張りたい”と思える形をつくれているサロンにある。成功パターンを学びながらやっていくことが大事だと思う。
●金内光信 理事長
組合(BA東京)は、「生衛法」(生活衛生関係営業の運営の適正化及び振興に関する法律)のもと、経営者が加入できる組合。美容室経営者になるには、税務申告(事業所届け)や保健所登録を必要とするが、フリーランス美容師はグレーな状態。というのも、我々の職業で最も重視されるべきは衛生管理にあるものの、フリーランスは事業所届けを出せば個人事業主になれるが、保健所では認められないのが現状。10万人がフリーランス美容師となったいま、では誰が衛生管理をするのかということが課題になっており、組合としては衛生管理を危惧し組合加入によって衛生を担保したいところ。組合加入資格については、「生衛法」第15条に「組合の組合員たる資格を有する者は、その地区内において当該業種に属する営業を営む者で定款で定めるものとする。」とあり、(組合加入資格に)施設を持たなければならないとは書いてない。では、法改正するのか、法律の拡大解釈を進めるのか、大きなテーマなだけに、内外にも呼び起こしたいと考える。
テーマ【美容師生涯教育のあり方、制度見直しの可能性】
2024年から始まった、厚生科学審議会 (生活衛生適正化分科会理容師・美容師専門委員会)で、理容師美容師の教育制度が話し合われているなか、美容サミットでは「教育のデジタル化」「管理美容師の役割」「即戦力の教育」についてなどが議論された。
●寺村優太(株式会社スリー 代表)
僕自身、現役で美容師をしながら、美容業界の問題を解決するために事業を行っており、特に力を入れているのがVRを使った美容の技術習得。2017年から始動し、現在、全国の美容学校16校、約4,700人の美容学生がVRで国家試験対策と技術習得をしている。今、美容学校が抱えている問題は学生の減少。特に地方都市が深刻で、各学校は差別化を図り、VR教育を取り入れることで入学者獲得に繋がっている。VR教育のメリットは技術習得期間の短縮にあるので、美容学校に通いながら、1年であってもより多くの技術習得が可能となる。国家試験対策とともにサロンで必要とされる実践的な教育も習得可能となるので、質の高い教育に繋がりやすく、サロンも実践的な教育をしてくれる学校から積極的に生徒を取ろうとなれば、求人票の出し方も変わってくると思う。
●福島吉範 副理事長
デジタル化の波はコロナ禍で加速した。全日本美容講師会でも教育動画の配信を話し合ったが実現にはいたっていない。ただ、今は待っているだけではお客様がくる時代ではないので、新しいものを積極的に取り入れて、発展していかなければならないと考える。
●森越道大(株式会社SENJYU 代表/一般社団法人デジタルサロン協会 事務局長)
約12・3年前、SNSの台頭で、自己ブランディングをはじめ美容業界の集客ルールが大きく変わった。それまでは、雑誌に掲載されるサロンがブランドサロンだったが、SNSを使いこなしたサロンがカリスマサロンといわれるように。そもそも美容文化と関係なく、テクノロジーの進化によって美容のルールがどんどん変わることに違和感を感じている。本来、美容師は目の前のお客様を幸せにすることが仕事で、これこそ大切な美容の文化のはず。当時Web2.0(SNSやブログ)が登場した時代にそこに飛びつくしかなかった美容業界だったが、次はそうではなく、新たなWeb3.0(AIやメタバース、NFT等)時代に、あくまでテクノロジーを手段として使うことを考えたい。そのためにデジタルサロン協会を立ち上げた。DXを推進したいわけではなく、目的は「お客様や自分たちの文化を守ることを推奨していくことが、これからの美容業界に大切だ」と考えている。
●青木大地(COA銀座 代表)
COAでは、サロンカリキュラムをVR動画化し、サロン教育に活用している。というのも、自身が経験したこととして、新卒で内定が決まりサロンの技術が分からないまま4月に入社し、生活や環境が変わるなか練習に励みつつサロンワークを覚えるのは結構ハードなことだったから。COAの新入社員には、入社するとゴーグルを送り、学習してからサロンに入ってもらっている。また、COAではインターンも受け入れており、美容学校に在学しながら即戦力を目指せるような取り組みを産学連携で行っている。
●間嶋崇裕(AMA TOKYO 代表)
管理美容師について思うのは、そもそも取った方がいいという感覚が薄いのが正直なところかと。具体的な活用シーンで考えてみると、例えば、公衆衛生上において新しい情報をもっている美容師であれば、アップデートされた管理美容師がいることに対する価値が生まれると思う。管理美容師がブランドになれば、スタッフ皆に取ってほしいと思う。
●金内光信 理事長
管理美容師については、2010年の制度行政刷新会議の事業仕分けで廃止対象になった経緯もあり、新しい役割があればポジションもあがるのではないか。例えば、管理美容師がいるサロンでは、実習生や研修生が管理美容師の管理下で仕事ができるという風になれば、本人もサロンも助かる。また、学校教育については、どうしても国家試験が主流の教育にならざるを得ないというのが実態。大学のように美容学校も1年目は、消毒学や美容は何たるかなど美容の基礎を学んで、1年目の終わりに国家試験をやればいいのでは。そして2年目は徹底して専門課程の勉強をしてもらう。ヘアに進むのか、エステなのかネイルに進むのか、専門をしっかり学べばサロンで役立つのではないか。
●佐藤勢津之(公益財団法人理容師美容師試験研修センター 部長)
管理美容師制度ができた経緯は、昭和38年の臨時行政調査会から始まる。当時、問題となったのが、美容師資格を持たない人による美容行為が行われているにも関わらず何の事故も起こっていないことから、名称独占に変更する規制緩和の対象に。これを受け、業界は過当競争を懸念し理美容業界と学校が立ち上がり、管理者として衛生管理に責任を持つことを目的に管理美容師制度ができた。そうした経緯から管理美容師の役割は「衛生的に管理する」という名目にあり、役割を増やすのであれば衛生に関したことがいい。補足すると、規定では、(インターンが)美容学校に在学中であれば、管理美容師がいるサロンでは美容行為ができるようにやっている。
1年目に国家試験が受けられないかについては、法解釈にもよる。(美容師法の第4条「美容師試験は、美容師として必要な知識及び技能について行う。」とあり)つまり、国家試験は「必要な知識及び技能について試験をする」という規定のもと、必要な知識技能を学校では必修科目として教え、必修科目がクリアしていれば、試験が受けられるということ。では、昔のインターン制度の1年と、今の必修科目の時間数を比べるとほぼ同じ。ちょっと頑張れば現在も1年で教えることは可能になる。また、即戦力を求める声を考慮すると、卒業と同時に免許証が付与されるような仕組みにして、2年目は選択科目として、学校に在籍しながら進みたい道でインターンをするのはできない話ではない。
あくまで私個人の考えで試験センターの将来で思うのは、学校の卒業認定と実技試験(国家試験)は同じ内容で、卒業認定を国家試験に替えることが可能だと思う。というのも、それぞれの学校が設けている卒業認定基準は国家試験合格レベルと謳っていて、一方、実技試験合格基準は養成施設卒業レベルとされており、つまりは同等。
昭和26年に試験を導入した、当時の理由として、養成施設やサロンの設備がさまざまだったため、欲しい人材のために試験が始まった。あれから70年以上が経ったが、根底には、業界がどういう人材を求めるかにあると思う。1年で国家試験課題ができ、そして、それを受け入れてもいいと組合・業界が賛同すれば、役所は動かざるを得ないのではないか。